
筋肥大させたいのですが、適切なトレーニング方法が分かりません。回数や頻度、重量はどのくらいがいいのでしょうか。

筋肥大を効果的に狙うためには、意識すべき点があります。少しでもトレーニングプランのデザインに役立てばと思います。
この記事ではそんな筋トレの前提知識を解説します。
・筋肥大を最大限に発揮させるトレーニング方法と意識
・トレーニングの考え方
結論から言うと、「筋力増強・筋肥大の効果=強度×頻度×回数(セット数)」で決まります。
様々な研究から導き出され、スポーツ医学や医療の現場では常識のようになっています。
「強度×頻度×回数(セット数)」というのは「総負荷量(ボリューム)」と同等です。
総負荷量が高ければそれが結果に出るのは当然、と思われますが、重要なのは総負荷量の捉え方です。
シンプルな例を挙げます。
①ベンチプレス100kg,8回,3セット=100×8×3=2400(kg)
②ベンチプレス30kg,10回,8セット=30×10×8=2400(kg)
一見、ベンチプレス100kgを挙げた人の方が筋トレの効果がありそうな印象ですが、総負荷量でみた時には30kgでも回数を重ねると100kgを挙げる人と同等のトレーニング効果が得られるということです。
それって、本当に効果あるの??そして同じ効果なの?
そう思われると思います。いくつか研究結果やレビューを集めてきましたので、参考にしてください。
筋肥大を効果的に狙うには【総負荷量】を意識しよう
筋肥大効果は総負荷量に依存
筋肥大には高強度トレーニングがよい?
よくトレーニングをしていると、「筋肥大をさせたければ高強度がよい」と聞きませんか?
これにはある根拠があります。
アメリカスポーツ医学会では、最大筋力(1RM)の60-70%以上の高強度運動で筋トレによる筋肥大の効果を最大限に引き出すことができるとしています。初心者は8-12回、中級者〜上級者は1-12回の回数を重ねることが効果的とも示しています。1)
他にも、この1RMを向上させるためには1RMの60-80%以上で回数を重ねる必要があると言われています。2)3)
これらの報告を受けて、筋トレ界では高強度がよい!という風潮となりました。
筋肥大への低強度トレーニング効果は?
それでは、低強度での筋トレは筋肥大に影響を与えないのでしょうか?
Burdらは、低強度のグループは高強度のグループよりも総負荷量が高くなり、筋タンパク質の合成率も増加した、と報告しています。4)
・被験者にレッグエクステンションを行わせる。
・最大筋力の90%の高強度群と最大筋力の30%の低強度群の2つのグループに分けて実施。
・それぞれの動作を疲労困憊まで行う。
【結果】
・総負荷量において、低強度トレーニングが高くなった。
・筋タンパク合成率が高強度群と低強度群では、低強度群の方が有意に高かった。
【参考】

(※参考文献より一部抜粋、編集)
総負荷量による筋肥大効果の違い
Burdらは総負荷量によるトレーニング効果の違いを報告しています。5)
・トレーニング経験者の被験者にレッグエクステンションを行わせる。
・最大筋力の70%の高強度で1セット行う群と3セット行う群に分けて実施。
・それぞれの動作を疲労困憊になるまで行う。
【結果】
・総負荷量は1セット群:942kg、3セット群:2,184kgと両者に有意な差がみられた。
・筋タンパク合成率が1セット群と3セット群では、3セット群の方が有意に高かった。
つまり、総負荷量が高いほど筋肥大を狙いやすくなるということが言えます。

なるほど。では筋肥大をさせるには必ず高強度でなくてはならないというわけではないのですね。重要なのは”総負荷量”…メモメモ..。
総負荷量は筋肥大の指標となるのか
では、実際にトレーニングを行う際に”総負荷量”は筋肥大の指標となるのでしょうか。

確かに、”総負荷量”が筋肥大の指標となるのであれば、筋トレメニューを組み立てやすくなりますね。

そうですね。指標ができればより理論的なメニューをデザインすることができます。少し、参考になりそうな報告を集めてきました。
Baz-Valleらは総負荷量が筋肥大のトレーニング量の定量化法の指標として、有効であるかを検証しています。7)
いわゆるシステマティックレビューというものです。
このレビューの対象は下記の通りです。
・ランダム化比較試験
・トレーニング頻度、総数、反復回数による筋肥大効果検証をしている
・6週間以上の継続したトレーニング
・被験者は最低1年間のトレーニング経験者
・年齢は18歳〜35歳
・直接的、又は間接的な評価方法を通じて形態学的変化を報告している
・既知の病状がない被験者
・研究が査読付きジャーナルに発表されている
この条件を全て満たす研究は14つ存在しました。
対象の14つの研究から導き出された内容は非常に信頼度が高いと言えます。
その解析結果は、強度と回数に総セット数を合わせた総負荷量は、筋肥大効果を示す有効な指標になることを示唆する、というものでした。
特に反復を行う範囲が6回以上の場合、セット数の総数はトレーニング量を定量化するのにより適切な方法のようです。
このレビュー内でBaz-Valleらは、筋肥大を狙う場合はトレーニングの総負荷量を指標として実施することが有効であると述べています。
しかしながら、過度な総負荷量によるオーバートレーニングは、筋肥大の効果を減少させてしまう可能性が示唆されています。
その場合はセット数を減らして総負荷量をコントロールすることを推奨しています。
いずれにせよ、総負荷量をベースにして、トレーニングをデザインすることが重要であると言えます。
トレーニングを管理する
総負荷量が筋肥大のための指標となることがわかりました。
しかし、実際に指標とするためには、日々の変化を把握していなければなりません。
よくトレーニーの方はトレーニングメニューを記録しているのを見かけますよね。
・ベンチプレス○kg○回○セット(レスト○分)..
・スクワット○kg○回○セット(レスト○分)..
と、休憩時間にメモしている人やアプリを使用し、記録している人など。
「日記」という位置付けで記録されている方もいますが、これは自分の成長が可視化できるだけでなく、トレーニングメニューをデザインする材料でもあるのです。
以前のトレーニングメニューと比較し、負荷量の増減、調整ができます。
どのペースで調整を行えばよいかわからないという方は一定の期間を決めて、負荷調整を行うとよいと思います。(例えば、○週間経過後、○kg増加、○回増加など)
より効果的なトレーニングを行い、筋肥大を狙うために記録習慣を身に付けることをお勧めします。
まとめ
・総負荷量は筋肥大の指標となる
・総負荷量は高い方が筋肥大効果が見込める
・低強度トレーニングでも回数、頻度で高強度トレーニングと同等の効果
・総負荷量を効果的な指標にするためにもトレーニング記録が有効

早速、総負荷量の管理をしつつ、効果的な指標として活用していきたいと思います。その他の要素としてトレーニング速度や休息なども影響すると聞きました。その関連要素についても詳しく知りたいです!

そうですね。トレーニングの速度や休息は非常に重要な要素です。追々解説していきますね。

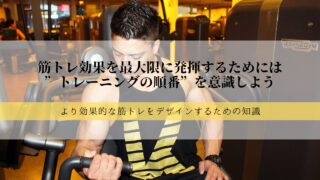
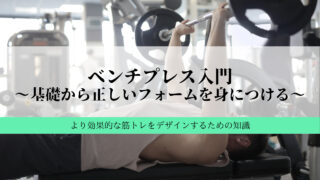



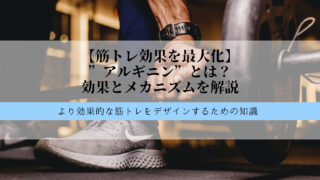
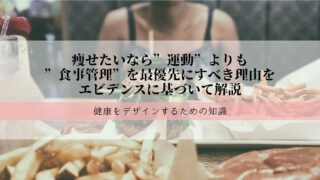

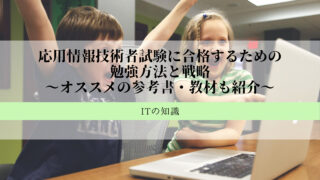




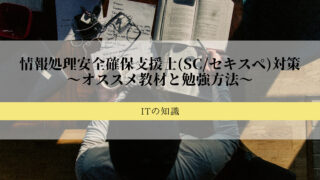


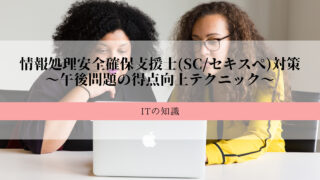





コメント