
筋トレをするとメンタルが強くなるってよくいうけど、それって本当?

確かによく聞きますよね。そんな疑問を解消するために、筋トレが与えるメンタルへの影響を根拠(データ)に基づいて紐解いていきたいと思います。
筋トレとメンタルの関係
筋トレでメンタルは強くなるのか
そもそも筋トレでメンタルは強くなるのか、という話ですよね。
筋トレがメンタルに与える効果は数々の論文で報告されています。
手法や考え方は多様なので、全ての人に当てはまるかと言われると分かりませんが、誰にでも当てはまる要素はきっとあるはずです。
私は筋トレでメンタルは強くなる、そう信じています。
根拠に基づきながら、みていきましょう。
<<<筋トレがメンタルを強くする?必見本特集>>>
日本人はメンタルが弱い??
日本人は「真面目だ」「勤勉だ」「根性がある」などと言われていますが、なぜこのように言われることが多いのでしょうか。
後にも記載しますが、脳内には「セロトニン」という神経伝達物質が存在しています。
セロトニンは安心感を与える、平常心を保つ、精神を安定させる、などの働きをします。
セロトニンは体内で再利用されるのですが、その際に活躍するのがセロトニントランスポーターです。
このセロトニントランスポーターは遺伝子量が多いL型と少ないS型に分類されており、
L型:セロトニンを多く生成→楽観的、精神が安定
S型:L型と比較し、少量→不安を感じやすい
となっています。
S型を持つ人はセロトニン量が少なく、行動に恐怖や不安が反映されるそうです。1)
そしてこのセロトニントランスポーターの割合は人種によって異なると言われており、欧米人はL型が多いのに対し、日本人はS型が多いとされています。2)
つまり、日本人は他人種と比較して不安を抱きやすい人種なのです。
そんな不安を払拭し、自信を身に付けるために「真面目」「勤勉性」といった行動でカバーする精神が国民性として広く広まっているのでしょうか。
え、メンタルの弱さは国民性?どうしろと?
最近のスポーツ医学や精神医学では、筋トレや運動がメンタルヘルスに効果があると数々の研究で明らかになっていますので、安心してください。
筋トレとメンタルに関連するデータ
Brett R Gordonらのメタアナリシスによる報告3)ではレジスタンスエクササイズトレーニングにより、健常者及び精神疾患を持つ被験者の不安症状を大幅に改善する、としています。
そして、その効果は手法や負荷、強度、性別などによる差はない、ようです。
Brendon Stubbsらによる不安、ストレスを持つ対象者への運動効果を研究したデータのメタアナリシス報告4)によると、運動は不安、ストレス関連の障害を持つ人の不安症状を改善するのに効果的であるとしています。
導き出されたデータから、運動が不安、ストレス疾患を持つ患者への重要な治療手段となり得る、とも報告しています。
また、レジスタンストレーニングのみならず、有酸素運動についても不安、ストレスへの肯定的な効果が立証されています3)。(特に有酸素運動のストレス、メンタルへの効力を示す報告は非常に多いです)
つまり、数々の研究結果から導き出されたメタアナリシスで肯定的な効果が認められていることから筋トレ(有酸素運動、レジスタンストレーニング)は不安、ストレス症状を改善しメンタルヘルスを向上させる、と言えるでしょう。
筋トレでメンタルが強化されるワケ
関連する要素は数多く存在しているとされていますが、中でも代表的な要素をまとめてみました。(書き切れないほど多いです)
セロトニン
セロトニンは様々な働きをします。
セロトニンは精神の安定や安心感や平常心、頭の回転をよくして直感力を上げるなど、脳を活発に働かせる鍵となる脳内物質です。特に、ストレスに対して効能があり、自らの体内で生成されるもので、精神安定剤とよく似た分子構造をしています。6)
「幸福感」を得られる要因の一つとして言われていますが、運動はセロトニンを活性化し、神経成長因子の発現低下を予防するとされているのです。5)
運動によりセロトニンが活性化されることで精神面が充実し、ストレスや不安に対して、効能があると言えます。
ドーパミン
向上心やモチベーション、記憶や学習能力運動機能に関与し、快楽を司り報酬系と呼ばれる神経伝達物質です。7)
そのドーパミンの分泌が筋トレや有酸素運動により促進されます。8)
運動後の爽快感はこのホルモンの影響と言われています。(脳内麻薬ですね..)
テストステロン
言わずと知れた男性ホルモンですが、テストステロンには筋肉、骨格、血液を形成し、男らしい風貌、肉体を作るとされています。
テストステロンは運動によって分泌が促進され、特に負荷の高い運動で分泌されます。9)
また、テストステロンは社会的地位、状況の変化や運動によって変動し、競争効果により増加します。10)
1:常に勝ち続ける群
2:常に負け続ける群
3:1回目に勝ち、2回目に負ける群
4:1回目に負け、2回目に勝つ群
に分類します。
それぞれの群でテストステロン値を分析すると
1、2の状況が変化しない群(安定層)に対して
3、4の状況が変化する(不安定層)にテストステロン の有意な増加が見られました。
つまり、状況や心理の変動が生じた際にテストステロンの効果を発揮しようとするわけです。(お助けホルモンです)
テストステロンは大きな決断を迫られているときなどにも分泌が増加するとも言われています。
筋トレを含む、運動をすることで、テストステロン分泌量を増やし、状況変化や心理変化に対応できるメンタルの強さを身に付けることができるのではないでしょうか。
成長ホルモン
エンドルフィン
エンドルフィンは忍耐力の構築や鎮痛効果があるとされており、ストレス反応に大きく関与しています。14)
心拍数が50%以上になる中等度以上の運動により分泌量が有意に増加することが報告されています。15)
別名「脳内モルヒネ」とも言われており、このホルモンにより脳内が活性し、不安や苦しみを和らげ精神的ストレスを緩和14)することができます。
その他、多くのホルモンが影響しています。
自己効力感・自尊心・満足感
筋トレが自尊心や自己効力感、満足感を向上させるということは数々の報告により明らかになっていますが、その一部を紹介します。
「自分自身への自信があること」
「自分には能力があり、やればできると感じること」と捉え、
学生の筋トレと自己効力感の変化を調査した。結論、自己効力感は向上した。理由は下記のように考察されている。
①達成経験と社会的説得
・対象者が自分で目標を設定し、その目標を達成できたこと
・目標達成時に他者から承認や共感を得たこと
②頻度と主体的参加
・少しずつ身体への変化が現れ、トレーニングしたいという気持ちが高まった
・小さな変化が継続の原動力となった
③身体の変化に伴う変化
・洋服を着た時の変化、身体を動かした時の違和感
→体感できるため、変化を可視化しやすく自己承認が可能
④プログラムの自己設定
・筋トレを継続しているうちに、セット数や負荷量などを対象者が自分で設定できるようになった
→自己管理、目標設定、達成のサイクルを実現
筋トレを行うことにより、はじめは中々気付きにくいかもしれませんが必ず身体には変化が起こります。
身体の変化や自身の取組に対する自己承認、そこから派生する他者承認によって自信とモチベーションが向上していきます。
スポーツ科学や心理学の分野における113本の論文で「筋トレは自尊心を保つ、もしくは高めること」が報告されています。17)
まとめ
数多くの要素から筋トレでメンタルが強くなる、ということを確認することができました。
根拠となる多くのデータも存在しています。
必死で努力して、自己管理を行い、身体の変化に気がつけた時、それは間違いなく自信になりますよね。
もし、すぐに変化が見られなかったとしても計画を達成できた自分、必死で努力した自分を褒めることで自己効力感、自尊心を養えると思います。
筋トレでメンタルは強くなります!

なるほど…やっぱり筋トレってメンタルにいい影響与えるのか。筋トレするしかないやん…!
参考文献
2)若年日本人男性におけるセロトニントランスポーター遺伝子多型と賞賛獲得欲求・拒否回避欲求の関連,岸田 文, 崔 多美, 綿貫 茂喜,日本生理人類学会誌,2016年 21巻 3号 p.115-119
5)うつ・不安にかかわる脳内神経活動と運動による抗うつ・抗不安効果,北 一郎, 大塚 友実, 西島 壮,スポーツ心理学研究,2010 第37巻 第2号 113-1401項
6)医療法人社団 平成医会 HP コラム「セロトニンの増加が心身に及ぼす効果」
11)Strobl JS, Thomas MJ. Human growth hormone. Pharmacol Rev. 1994;46(1):1‐34.
12)Rosen CJ. Growth hormone and aging. Endocrine. 2000;12(2):197‐201. doi:10.1385/ENDO:12:2:197
13)運動強度(METs)と成長ホルモン分泌の関連について,宇都宮由依子 橋田 誠一,徳島文理大学研究紀要 第 96 号 平成 30.9
17)超筋トレが最強のソリューションである 筋肉が人生を変える超科学的な理由,Testosterone ,久保孝史,福島モンタ,文響社,2018


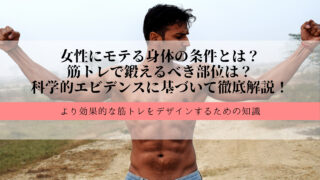

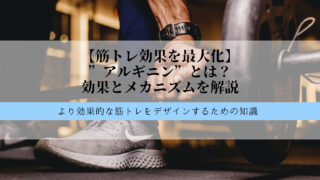

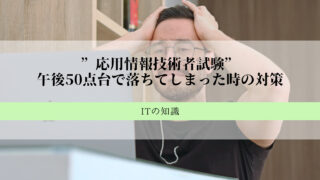



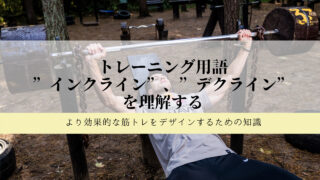
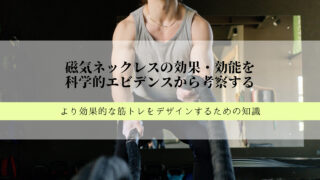


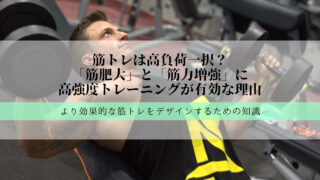

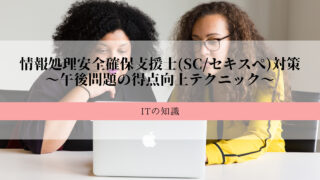





コメント