仕事の目的や計画を明確に立て、修正しながら効率的に実行できる人、多くの情報を得ながら同時に複雑な処理をすることができる人、状況に応じて柔軟に代替案や解決案を模索することができる人は現代の知識社会において重宝され、デキる人と評価されます。
そのようなデキる人の前提条件は認知機能を高水準で発揮することにあります。(※認知機能:記憶・思考・理解・計算・言語・判断といった知的能力を用いて、ものごとを正しく理解して適切に実行する機能)

しかし、太るとこれらの認知機能が低下してしまう可能性があるのです。
「流石に関係ないでしょ」と思う人もいるかもしれませんが、昨今の行動神経科学における研究結果から太ると認知機能が低下してしまうことが示唆されています。
この記事では「太ると認知機能が低下する」エビデンスをご紹介します。
【本当?】太ると頭が悪くなる?
認知機能とは
認知機能とは「記憶・思考・理解・計算・言語・判断といった知的能力を用いて、ものごとを正しく理解して適切に実行する機能」のことです。
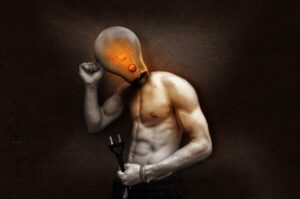
この認知機能領域ですが、DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Ⅴ)において「複雑性注意」「実行機能」「学習と記憶」「言語」「知覚・運動」「社会的認知」の6領域に分類されています。1)
| 認知機能の分類 | |
| 複雑性注意 | 複数対象への注意の集中、持続、選択できる機能。 |
| 実行機能 | 複雑な課題の遂行に際し、課題ルールの維持やスイッチング、情報の更新などを行うことで、思考や行動を制御する機能。 |
| 学習と記憶 | 自分の体験した出来事や過去についての記憶を保存し、再生できる機能。短期記憶、長期記憶、潜在学習など。 |
| 知覚・運動 | 環境や具体的刺激状況の知覚に基づいて、身体的動作を協応させる機能。 |
| 社会的認知 | 他者の表情、言動、行動などから相手の感情や意思を推測し、その過程から自己の生存に必要な意思決定が行われ、円滑な対人関係を形成し、維持していくために必要な機能。 |
前述しましたが、社会で求められるデキる人は上記の認知機能を高い水準で発揮することを求められます。
では、肥満は認知機能にどのような影響を与えるのでしょうか。
肥満が認知機能に与える影響
太ると抑制コントロールなどの認知機能が低下する
Yangらによるメタアナリシスを紹介しましょう。Yangらは肥満による認知機能への影響を調査した結果を解析しました。
概要は以下の通りです。
定義:BMI30以上が肥満、BMI25-30が太りすぎ
内容:肥満や太りすぎと正常体重による認知機能(抑制コントロール、ワーキングメモリ、認知の柔軟性など)への影響を解析
その結果、肥満では、抑制コントロール、ワーキングメモリ、認知の柔軟性の低下が認められました。さらに意思決定、話の流暢さ、計画の実施といった他の認知機能の低下も認められました。また、太りすぎでは抑制コントロールとワーキングメモリで低下を認めました。
サブグループ解析結果からこれらの認知機能の低下に年齢、性別は影響しないことが推測されました。
太りすぎでは抑制コントロール、ワーキングメモリの低下に留まりましたが、肥満になると抑制コントロール、ワーキングメモリ、認知の柔軟性に加えて、意思決定、話の流暢さ、計画の実施といった認知機能全般の低下が生じるエビデンスが示されたのです。

太ると認知機能への影響がすごいですね。気をつけないと。。。
これらの結果から、太ると認知機能が低下することが示唆されました。
では、なぜ太ると認知機能が低下するのでしょうか。
次回はそのメカニズムについて、紐解いていきましょう。
参考文献
1)DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル,日本精神神経学会日本語版用語監修,【監訳】高橋三郎,大野裕,【訳】染矢俊幸,神庭重信,尾崎紀夫,三村將,村井俊哉,585-587,医学書林,2014



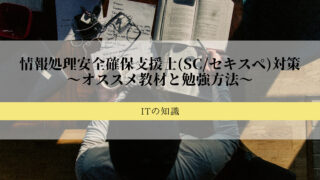





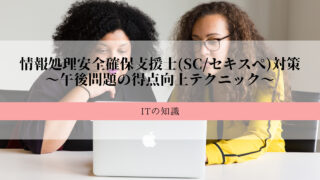

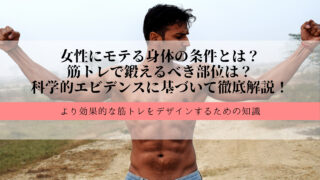

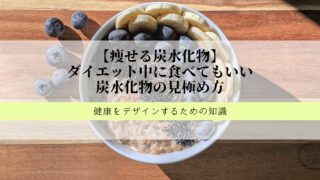




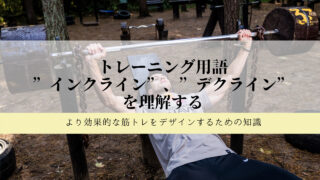



コメント