「情報処理安全確保支援士(通称:SC、セキスぺ)」
高度資格の保有は、より専門性が高く高度なスキルを持つことを示し、就活や転職の時にも役に立ちます。
しかし、高度資格であるため、合格率は10%台と狭き門となっており、しっかりと対策を行わければ合格が難しい資格です。
特に記述形式の午後Ⅰ、午後Ⅱ問題が鬼門となっており、対策に悩む方が多いのではないでしょうか。
この記事では「午後問題の対策はどうすれば…」、「得点力を向上させるテクニックがあれば教えてほしい」という方向けに、合格時の実体験をもとにSC午後問題の得点力を向上させるテクニックを紹介したいと思います。
情報処理安全確保支援士(SC/セキスぺ)対策~午後問題の得点向上テクニック~
情報処理安全確保支援士の学習方針
全体的な学習方針や具体的な過去問演習方法などは以下の記事でまとめています。

得点力を向上させるテクニック
試験対策で実践していた、得点力を向上させるテクニックを紹介します。
長文読解のコツ
午後Ⅰの問題は、1問当たり約5~6ページで構成されています。
1ページにどの程度の時間をかければよいでしょうか?
1ページに2分かけたとすると、全体で5~6ページになりますので、合計10~12分必要になる計算です。午後Ⅰは1問に40分で解答したいので、問題文を読む時間だけで全体の30%の時間を消費してしまうことになります。
また、問題文は一度読めばよいというものでもなく、設問のたびに随時読み直す必要があります。下手をすると、ほとんどの時間を問題文を読む時間に費やしてしまうこともあるかもしれません。
そのため、得点力を向上させるためには効果的に問題文を読み解く力が必要になります。
簡単にいうと、「どこに、何が書いてあるのか」を推測し、自ら設問のヒントを探しにいくイメージです。

問題文を漠然と読まされる意識ではなく、謎を解くように目的意識を持って能動的に読み解いていく感じです。
そのために必要なのは、”セキュリティに関する知識”に加え、過去問をベースとした文章構成のパターンや設問での問われ方の情報です。この部分は、過去問演習を通して、対策を行うことが可能です。
この意識をもって過去問演習を行うと、より理解が深まるはずです。
ここでは、午後Ⅰ、午後Ⅱに共通する着目点を紹介しておきます。参考にしてみてください。
情報セキュリティポリシーを確認する
おそらくすべての問題において、登場する企業、組織に”情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)”が設定されているはずです。まずはここをチェックです。
「ISMS」や「セキュリティポリシー」、「情報セキュリティ委員会」といった言葉が登場したら、チェックしておきます。
この部分は後の設問で問われやすいポイントです。
・XX社にはISMSが設定されているか
・セキュリティポリシーは定期的に見直しが実施されているか
・セキュリティポリシーは最新版が運用されているか
・セキュリティ教育は徹底されているか
・セキュリティポリシーの抜け穴はないか など
組織体制を確認する
〇〇委員会(情報セキュリティ委員会など)の名称が出てきた場合や、組織図が記載されている場合にはその体制をチェックします。
・設定されている体制は正常に機能しているか
セキュリティポリシーの詳細情報を確認する
問題文の中で具体的なセキュリティポリシーが記載されていることがあります。その場合は要チェックです。(XX社個別の実施基準、運用マニュアルのような表現で登場することもあります。)
そして、重要なのは、すべての設問において、対策を検討する場合に、指標となるのは登場したセキュリティポリシーとなる点です。
見落とさないために、当内容が登場したらマークしておきましょう。
記述解答のコツ
問われていることを解答する
”問われていることを解答する”とは、設問の最後の内容を解答要素に盛り込むということです。
具体的には、以下のようなイメージです。
・「~の対策を述べよ」→「~という対策」
・「実施すべき作業」→「~という作業」
・「留意すべき内容」→「~ということ」
当たり前に感じるかもしれませんが、試験本番では意外と凡ミスしがちな部分です。解答時には、設問の文末表現に合わせる形で解答するように心がけるとよいと思います。
解答は8割以上の文字数を目標にする
前提として、8割の文字数に満たないと減点されるのかというと、そうではありません。
基本的には「△△字で述べよ」という設定には背景があると考えられます。(例えば、問題作成時に考えた解答例が25文字程度になったため、30文字以内という条件を設定した、という感じ)
ですので、解答例の記述ボリュームを狙って設定文字数の8割の記述を目指す形です。
IPAから、極端に短い解答例がごく稀に公表される場合があるので、あくまでも指標として認識しておいてください。
解答の下書きはしない
特に午後Ⅰは時間との闘いになります。(時間に余裕がある場合は、解答の下書きをして文字数調整を行ってもよいですが、基本的にはそんな時間はないと思っておいた方がよいです)
自分は以下のイメージで解答していました。
「最終的な文字数調整は文末表現で行う」
と言っても、中々難しいのでいくつかポイントを紹介します。
文節で考える
「文節で考える」とは1文節を10文字程度で設定するイメージです。(例えば、「30文字以内」であれば「3文節で解答(〇〇が、△△で、~~だ)」という感じです)
設問に文字数を設定するということは、解答レベルを指定しているということになります。

一緒に試験対策をしていた友人に教えてもらって、”なるほど!”と感じた内容なので書き記しておきます。
具体的には以下のイメージです。
20文字以内:形容詞をつけた単語、簡潔な文章(=2文節)
30文字以内:主語+目的語+述語の簡潔な文章(=3文節)★頻出
40文字以内:5W1Hの中のいくつかの要素など、少し具体化された文章(=4文節)★
頻出は「30~40文字以内」という指定の印象です。なので、「30文字」で解答する練習をして、文字数の増減に合わせて解答粒度を調整できるようにしておくとベストだと思います。
文末で調整する
例えば、30文字以内で解答する場合をイメージします。
(「〇〇が、△△で、~~だから」など)
②解答用紙に「〇〇が、△△で」まで書き込んだ時点の残り文字数を確認する
③残りの文字数に応じて調整する
残り文字数が少ない時:「~から」、「~の為」、「~という点」などで簡易的に調整
残り文字数に余裕がある時:「~という点が理由となる」など
IPAの解答例をみると、「~から」という例が多い、かつ文字数制限ギリギリになることは少ないです。
そこまで神経質に文字数や、文末表現にこだわる必要はないかもしれませんが、1つのテクニックとして紹介しました。
効率良く解答するコツ
効率良く問題を解き進めるために、「速く正確に問題文を読む」こと以外にもいくつかポイントがあります。
解答の候補となる用語を見逃さない
「情報セキュリティ関連の用語を見たときに、その用語に関連するキーワードを瞬時にイメージできること」が重要です。
重要な理由は、問題文を読み進めながら次に必要な情報を推測しながら読み進めることができるからです。
・必要になりそうな情報を推測する
具体的には、”ディジタル署名”という用語が出てきた時に、”なりすまし防止”、”否認の防止”、”改ざんの検知”といったディジタル署名で実現できることや、”公開鍵暗号方式”や”ハッシュ関数”などディジタル署名の仕組みに関連する内容を瞬時にイメージできるという感じです。
関連知識を瞬時にアウトプットできると、長文読解をスムーズに行うことができますし、解答時間の短縮にも繋がります。

また、実際に正答できるかどうかが、知識量によって左右される場面もあります。そのような問題を取りこぼさないためにも、必要になる知識の絶対量を増やすことは必要になります。
設問形式を判断する
午後問題選択に当たって、まず設問の形式を判断することが重要です。
設問形式を把握することで、時間のかけ方や解答の方法に検討ができます。(また、苦手な形式が多く含まれている場合にはほかの問題に逃げることも可能です)
設問の形式は大きく以下に分類されます。
・計算問題
・選択問題
・記述問題
そして、記述問題に関してはさらに詳細化できます。
①知識で解答できる問題
②問題文から解答を抜粋する問題
③問題文から解答の要点を抜き出し、加工する問題
順にみていきます。
穴埋め問題
問題文中に設定されている”知識を問う”問題や、問題中に記載されている図などを完成させる問題があります。
問題文中に出てきた穴埋め問題は、その前後の言葉を頼りにして、知識を元に解答を導きます。(ここは基本的に知識がなければ解答できないので、時間もかからない部分です。即答できない場合、諦めますw)
図に設定されている穴埋めの場合、問題文中にヒントがある場合があります。が、基本的には知識ベースで問われることが多い印象です。
穴埋め問題は基本的に解答が一意になるで、正誤がはっきり分かれます。取りこぼしが内容に対策をしておきたい部分です。
計算問題
計算問題で意識すべきことは”数字探しに時間をかけないこと”です。
体感ですが、この試験ではそこまで難易度の高い計算問題は出ないような気がします。なので、問題文に記載されている数字を的確に拾うことができるか、という点がポイントになります。
問題文を読むタイミングで、必要になりそうな数字にはマークをしておくとよいです。
選択問題
こちらは穴埋め問題と同様です。知識を元に解答するパターンと、問題文中のヒントを読み解くパターンがあります。
記述問題
①知識で解答できる問題
こちらはシンプルで、問題文を確認する必要なく、知識ベースで解答できる問題になります。
②問題文から解答を抜粋する問題
こちらは問題文中に、制約事項や背景、キーワードが存在する問題です。そして、該当部分を解答として抜き出す形式です。
③問題文から解答の要点を抜き出し、加工する問題
こちらは問題文中に、制約事項や背景、キーワードが存在する問題、かつ、該当部分を抜き出し、自分の言葉で解答をする必要がある問題です。
これらのパターンに必ずしも当てはまるわけではないですが(混合しているものもあったりするので..)、設問のパターンとして抑えておくとよいです。
ここで重要なのは、分類の見極めではなく、それぞれの問題に対する解答方法(対応方法)を決めることです。
解答例を確認して”なんだそんなことか”と納得する人
午後対策をしていて以下のような悩みを抱く方は多いのではないでしょうか?
・なんとなく解答のイメージはできるけど、うまく表現できない
・設問の意図はわかる、解答も大体わかる、どうすれば的確に表現できるのか
・解答例を見れば納得できる
こうした悩みを持っている方は基礎的な知識や経験を持ち合わせており、過去問をそれほど難しいとは感じないことも多いと思われます。解答の元となる知識を保有している状態にあるため、あとは解答を導くテクニックを補強することがカギとなります。これは、”自分の言葉を問題文中の言葉に置き換える”ことで解決できるかもしれません。
具体的には以下の流れです。
<STEP2>字数が足りない場合、内容を少し肉付けする(5WH1などの要素を盛り込む)
<STEP3>自分の言葉を問題文に出てくる言葉で置き換えられないか検討する(そのために、問題文のマーク箇所をチェックする)
<STPE4>設問の制限時数に収まるように、不要な部分をカットする
上手く解答できない場合は、自分の言葉にこだわりすぎているかもしれません。
解答例はあくまでも問題文中の言葉や表現に即して作られていることが多いです。なので、問題文の言葉や表現に自分の解答を寄せていくイメージを持つと、案外ドンピシャな解答ができたりします。
この辺りは慣れもあるかと思うので、何度か練習をしてみることをオススメします。
どうしても対策がうまくいかないとき
どうしても自分で学習が進められない場合やどこから手をつけたらいいか分からないといった場合にはオンライン講座の利用を検討してみるのもいいかもしれません。
オンライン講座の場合は過去問道場と同様で、場所や環境に縛られずにスマートフォンやタブレットで手軽にインプットやアウトプットができるため、自由度が高いです。
例えば、SC対策に特化した「支援士ゼミ」というオンライン講座があります。
過去問の解説動画に加え、午後試験で問われることが多いセキュリティ関連の時事ニュースを取り扱った講義動画や、直前対策講座で合格に必要な力を養うことができます。
講師に気軽に相談できたり、ゼミ生同士で交流できるチャットルームも存在しており、モチベーションの維持を図ることも可能です。
支援士を効率よく学習できる環境を多数提供されているので「一人で学習のモチベーションを維持できない..!」という方には嬉しいコンテンツかもしれません。
また、圧倒的に価格が低くてコスパの点で優れているのも嬉しいポイントです。
このようなオンライン講座も多数存在しているので、より学習時間を短縮化したい、効率よく学習したいという方は検討してみてはいかがでしょうか。
オススメの参考書
最後にお勧めの参考書を紹介します。

僕はこの参考書のみを使用しました。あとは、IPAの過去問題を反復演習です。
情報処理安全確保支援士「専門知識+午後問題」の重点対策
本書で勉強の進め方、午後問題の解法、問題文の読み進め方、抑えておくべき基本知識をまるっとカバーすることができます。
この「午後対策本」を1冊繰り返しやりこめば、強固な知識の土台ができ、解答力にも磨きがかかります。
短期間の学習で驚くほどの実力が備わっているはずです。
まとめ
合格する人と不合格の人は紙一重です。
合否ギリギリの人は、「穴埋めを1問正解できた」や「問題文のヒントをうまく使って解答できた」など、その一問の答案の書き方一つで合否が左右されることもあります。
この記事に記載したテクニックや考え方を上手く活用して、1点多く得点できることを願っております!
・情報セキュリティポリシーを確認する
・組織体制を確認する
・セキュリティポリシーの詳細情報を確認する
◆記述解答
・設問の意図を汲んで解答する
・解答は8割以上の文字数を目標にする
・文字数指定は文節で対応、文末で調整
◆効率良く的確な解答をするために
・解答の候補となる用語を見逃さない
・自分の言葉を問題文中の言葉に置き換える
合わせて読みたい記事


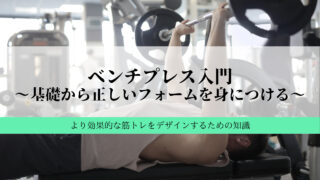



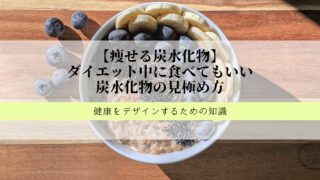



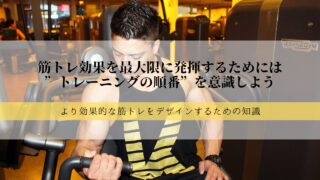

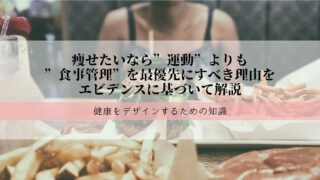


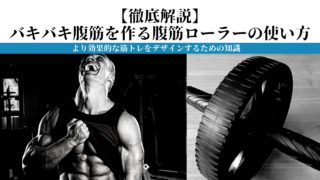
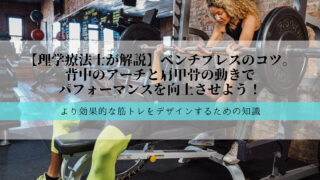
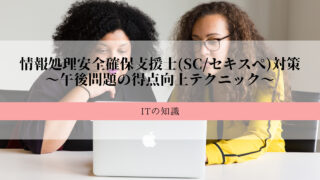


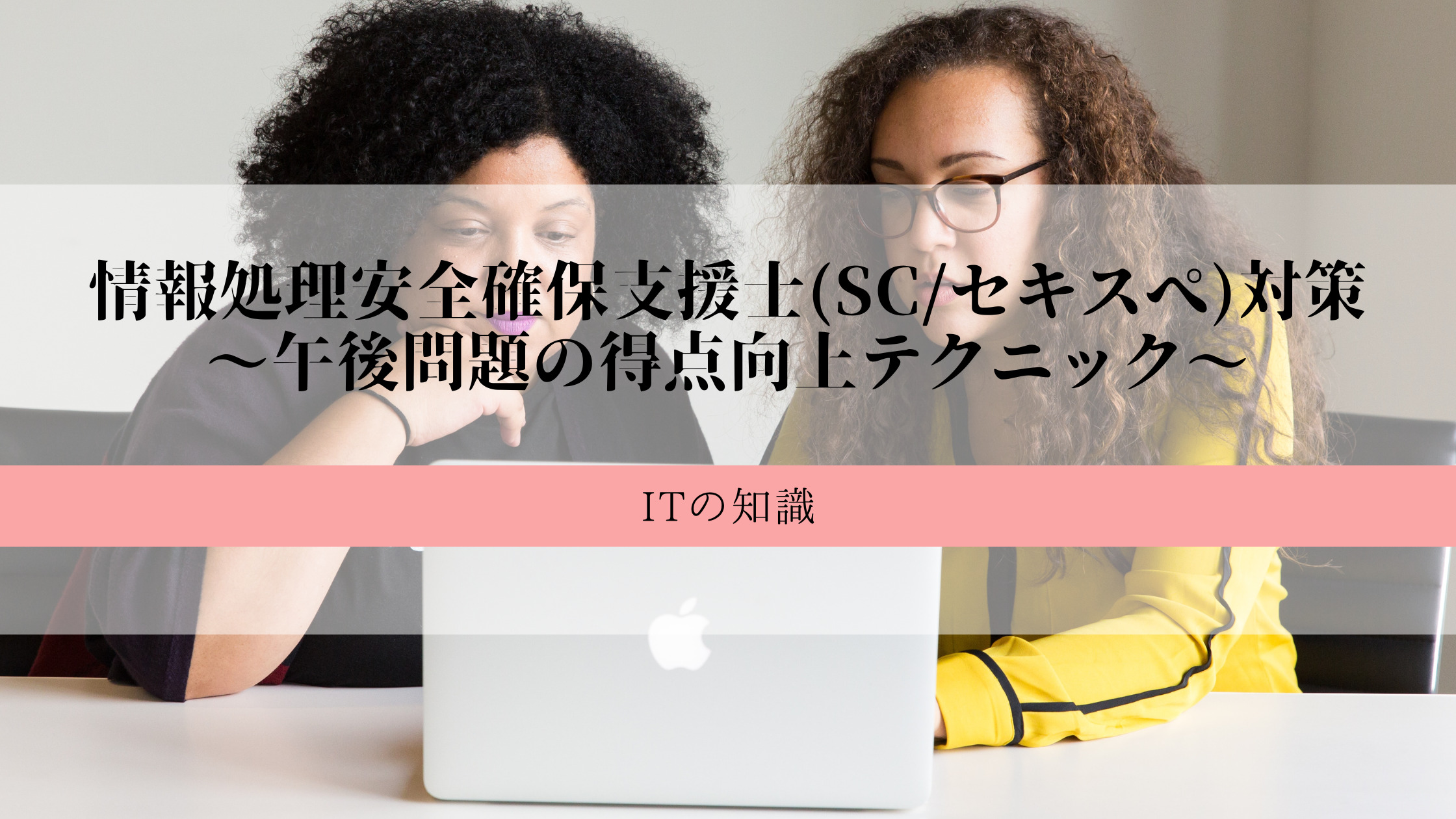


コメント