皆さんは音楽を聴きながらトレーニングをしていますか?
多くの人が音楽を聴きながら、または音楽が流れている環境でトレーニングしたことがあると思います。
また、テレビでオリンピックや各種スポーツの世界大会を見ていると、音楽を聴きながらウォーミングアップを行う選手の姿が映されていますよね。
一般トレーニーからトップレベルの選手まで音楽を聴きながらトレーニングをしていることや、ジムなどのトレーニング施設は音楽が流れている環境が多いということを考えると、トレーニングと音楽には密な関係がありそうです。
この記事では、「音楽がもたらすトレーニングへの影響」について考察します。
【筋トレ】パフォーマンス向上?トレーニング中に音楽を聴く効果について
音楽がもたらす身体への影響
はじめに、音楽を聴くことによる身体への影響について簡単にまとめます。
音楽の身体への影響については、以下の3種類で分類されることが多いです。
②遅いテンポの音楽
③自分が好きな音楽
そして、これらの音楽の効果はそれぞれ異なります。1)2)3)4)5)
効果についてざっくり以下の表にまとめました。

このように,音楽を聴くだけで私たちの身体には様々な影響があることが研究によって明らかにされています。

確かに静かな音楽を聴いている時は落ち着きますね。アップテンポな音楽を聴いている時はドキドキ鼓動が高まる気分です。イベント会場など、気分を盛り上げたい場面で使われているようなイメージです!身体への影響についてはおおよそ分かりましたが、トレーニングにはどのような影響があるのですか?
音楽がもたらすトレーニングへの影響
音楽を聴くことによるトレーニングへの影響について考察したいと思います。
トレーニングといっても種類は様々です。ここでは、ウォーキング、ジョギング、サイクリングといった低強度のトレーニングと疲労困憊まで追い込むような高強度のトレーニングに分けて影響をみていきたいと思います。
低強度トレーニングと音楽
まずは低強度トレーニングです。
低強度トレーニングを対象とした研究では、トレーニング中に音楽を聴きながら効果を検証したものが多いです。
山下らの研究では、最大酸素摂取量の40%にあたる強度の運動中に音楽を聴いた場合と聴かなかった場合の主観的運動強度をボルグスケール(RPE)を用い、その数値を比較しました。6)
その結果、音楽を聴いた場合の方がRPEが有意に低い値を示したことを報告しています。(RPE値が低いほど疲労感が少ないということになります。)しかし、心拍数には有意差が認められなかったことも報告しています。つまり、同じ運動強度でも音楽を聴きながら運動した場合は音楽を聴かずに運動した場合よりも疲れを感じにくいことが示唆されています。
主観的運動強度(RPE)
RPEとは、Rating of Perceived Exertionの頭文字をとったもので、トレーニングや運動の主観的なきつさ・疲労度を数字で表したものです。数値化するために6〜20の数字できつさを表す「Borg Scale」(ボルグスケール、グンナー・ボルグ氏が提唱)が一般的に用いられます。客観的な運動強度の計測が難しい状況でも記録が可能で、日々のコンディション変化を捉えたり、トレーニング負荷をコントロールするための客観的指標として用いられます。
※Borg Scaleと心拍数の目安
| 数値 | 自覚度 | 運動強度(%) | 心拍数(拍/分) |
| 20 | もうだめ | 100 | 200 |
| 19 | 非常にきつい | ||
| 18 | 180 | ||
| 17 | かなりきつい | ||
| 16 | 160 | ||
| 15 | きつい | ||
| 14 | 140 | ||
| 13 | ややきつい | 50 | |
| 12 | 120 | ||
| 11 | 楽に感じる | ||
| 10 | 100 | ||
| 9 | かなり楽に感じる | ||
| 8 | 80 | ||
| 7 | 非常に楽に感じる | ||
| 6 | 安静 | 0 | 60 |
このように疲労感軽減やパフォーマンスが向上する(走行距離が増加する)理由の一つとして、以下の理由が考えられています。
Baconらによると、音楽のテンポに自分の動きを合わせることでペースを一定に保つことができ,無駄なペースの乱れを抑えることができることから運動を効率的になると報告しています。8)
低強度トレーニングにおいて、音楽を聴くことは運動へ良い影響を与える可能性があるといえますね。
高強度トレーニングと音楽
次に高強度トレーニングについてです。
Youngらはトレッドミル運動負荷試験において,音楽を聴く場合と聴かない場合の心拍数とRPEには差が認められなかったことを報告しています。また、音楽が訓練を受けた個人のランニングパフォーマンスや努力の認識に影響を与えないことを示唆しています。9)
血圧や心電図の記録、各種身体状況をモニターしながら傾斜・スピードを変えて負荷を徐々に高める運動負荷試験のことです。一般的に負荷は最大心拍数の80~90%(目標心拍数)に達した時点で中止します。最大心拍数とは「運動量を漸増させてもそれ以上心拍数が増加しない最大運動時の心拍数」のことです。またそれまでに症状や兆候が出現すれば中止します(症候限界性)。負荷の方法については様々なプロトコルが存在しており、その代表格はBruce法ですが、基本的には「多段階漸増式の負荷であること、速度と傾斜を変えることにより負荷量を漸増すること」がポイントになります。
Bharaniらはトレッドミル運動負荷試験において、各運動強度でのRPEを音楽を聴く場合と聴かない場合の2条件で測定しました。10)低強度では音楽を聴く場合の方がRPEは低い値だったが、疲労困憊の状態に近づくにつれ音楽を聴かなかった条件下でのRPEの値に近づいたことを報告しています。
これらのことから,疲労困憊に陥るほどの高強度トレーニングでは音楽の影響が少ない可能性があると考えられます。
この原因としてKarageorghisらは、高強度運動では音楽による刺激よりも運動による身体への刺激の方が強くなることを挙げています。11)

トレーニング強度が高くなりすぎると、音楽どころじゃなくなるのですね..!トレーニング強度が高いといっても、疲労困憊まで追い込まない瞬間的な筋力発揮が求められるような場合にはどうなるのですか?
まず、Karageorghisらの研究をご紹介しましょう。
Karageorghisらは音楽のテンポ差異による握力への影響について調べました。12)13)その結果、テンポの速い曲を聴いた後の方が音楽を聴かなかった場合よりも握力の値が高いこと、テンポの低い音楽よりもテンポの高い音楽を聴いた方が高い握力数値となることが報告されています。
また、Hallらの研究ではテンポの速い曲を聞いた後の方が音楽を聴かなかった場合よりも60m走のタイムが向上したことを報告しています。14)走るだけでなく、水泳、握力でもパフォーマンスが向上し、15)ベンチプレスでもパフォーマンスが向上する可能性16)が示唆されています。
これらの研究結果から考えても、高強度運動の中でも疲労困憊に陥ることなく終了する運動(瞬間的に最大出力が求められる種目)であれば音楽の効果が期待できそうです。
また、上記の研究はトレーニング前に音楽を聴く場合の測定、トレーニング中に音楽をいく場合の測定を対象としています。対象の音楽は様々ですが、アップテンポかつ好みの音楽が効果が高いことが考えられます。
スポーツ競技の場面や、瞬間的に出力を高める必要がある場面には、ウォーミングアップで音楽を聴くことで競技パフォーマンスの向上に繋げられるのではないでしょうか。

トップアスリートのウォーミングアップ場面で音楽を聴く姿にはこのような背景があったのですね!私も音楽を競技パフォーマンス向上に繋げたいと思います。
まとめ
トレーニングや運動の内容によって、音楽による影響が期待できるものと期待できないものがあるようです。また、自分の好みの音楽や速いテンポの音楽がパフォーマンスに良い影響を与えるとされています。
→疲労感軽減、パフォーマンス向上の可能性
●高強度トレーニング
→①持続的に身体負荷が高まる運動:効果が少ない可能性(運動による身体刺激が音楽による刺激を上回ってしまうため)
→②瞬間的な出力が求められる運動:パフォーマンス向上の可能性
●音楽の種類
→アップテンポかつ自分の好みの音楽がパフォーマンスを向上させる可能性
→テンポの遅い音楽はパフォーマンスを低下させる可能性(疲労回復には◎)
参考文献
14)Hall K.G. and Erickson B.(1995)The effects of preparatory arousal on sixty-meter dash performance. The Applied Research in Coaching and Athletics Annual10 : 70-79.

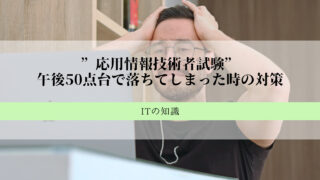
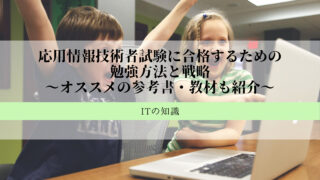
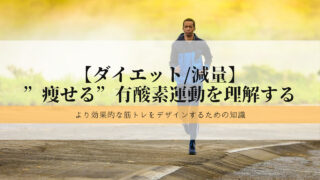
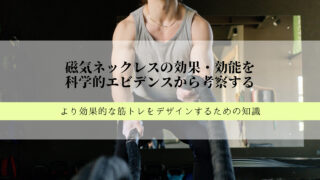







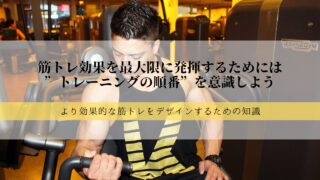


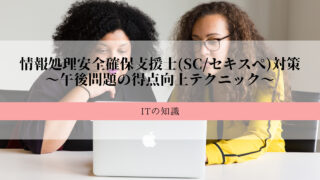






コメント